史実を元に、大隅の山林を守った3代の記録を小説仕立てにした本『大隅・山の守り人』(岩元定幸 著、 株式会社盈進社)が出版されました。
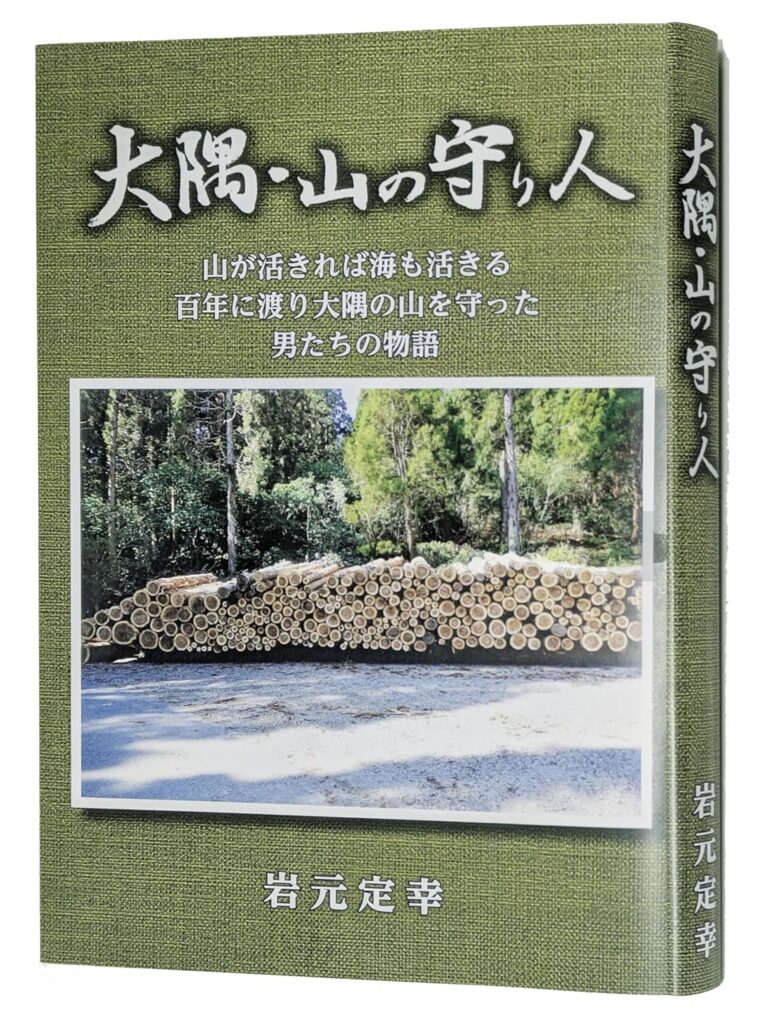
以下にこの本の概要を紹介します。
明治の初期から御用商人として鹿児島で早くから名を知られていた永吉柳右衛門は、その人脈の広さから軍部の情報をもとに商売を拡大したいと考えていた。
大隅の山地が膨大で豊かな山林が広がっていることに気づき、新たな商売ができないかと考えた。内之浦の岸良から田代のあたりの山々が、その昔北郷家の所領であったが、やがて島津家のものになっていることもわかった。しかし明治期に入ってからの山林管理の区別(国有林、県有林、市有林など)が不明確になっていることから、自分でも購入できるのではと考え始めた。
永吉は田代村役場に勤めていた日高助市を引き抜いて、山林の調査を始め、大隅山地が膨大で豊かな山林が広がっていることに気づいた。ある日、県の係官から岸良あたりの山林が「その昔島津義弘公が蒲生地頭の山田昌厳(有栄)のお狩場として下賜した。その地図を持っている人がいる」との情報を得た。
そこから時間はかかったが、永吉柳右衛門は山田昌厳の山林の権利を譲り受けることになり、永吉興業株式会社を設立して、従業員を集めて山林経営が始まった。従業員には信心深い者が多いことから、二ヶ所に山の守り神(山神神社)を作り、安全祈願もした。以下は、最初に岸良の山中に造った姫門神社の現在の写真である。

現場では日高助市が中心となって、木炭や用材を運搬するルートの開拓から始め、次第に事業を拡大していった。明治36年正月に、日高助市は郡役所に勤めていた小榎信吾に会社の管理者として入社を誘い、信吾は7月に鹿屋の郡役所を退所して田代の実家に戻り、会社勤めを始めた。その後、軍馬用飼料、燃料用薪材、鉄道用枕木の生産が増えたため、会社事業の拡大に対応するために従業員を増やした。以下は切り出された材木の写真である。

その後、日高助市に次ぎ、永吉柳右衛門が亡くなり、事業が次第に縮小して、経営者も変わった。小榎信吾は人減らしをしながらも、新しい材料として瓦屋根の下地に使う平木の販売を始めた。しかし、大正の終わりごろになると輸入材が増え始め、国内の林業経営も苦しくなった。
小榎信吾の一人息子の信雄は、高須小学校で教鞭をとっていたが、鹿屋中学の恩師の4年先輩から勧誘されて、昭和12年10月に満州鉄道に入社し鉄道員として働いた。しかし昭和12年7月に発生した盧溝橋事件を発端にして日中韓の小競り合いが起こり、その後に戦争となった。昭和20年8月15日に終戦となり、小榎信雄は12月に引揚船に乗り帰国した。
昭和21年3月に小榎信吾が亡くなり、息子の信雄は山形屋綿店の所有となっていた会社に入り、父親の後を引き継いで山の管理をすることになった。以下は小榎信雄が三男の修と、山の勘場の宿舎で語らう写真である。

その後に会社が日本パルプ株式会社に変わり、日本の経済復興とともに林業事情も元気になってきた。小榎信雄の山の仕事は順調であったが、会社の経営方針が変わり山林を県に買い上げてもらうことになり、信雄は県の職員となって山林の管理を続け、平成4年に74歳で退職した。
この100年近い期間、親子を含め三代にわたり大隅の山の管理を続けることで、荒廃した山もよみがえった。その功績は大きく、まさに『山の守り人』であった。
この本は大隅の近世と現代の歴史の貴重な記録書でもあります。なお、本書には大隅の山林事業の栄枯盛衰の他に、庶民の生活、鉄道、学校、桜島の噴火などの史実や多くの人物(例えば玉川学園の創立者の小原國芳)も登場しますが、長くなるので割愛しました。
(文責:朝倉悦郎)